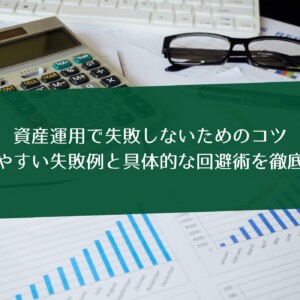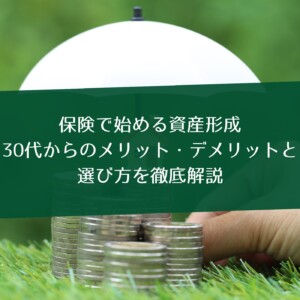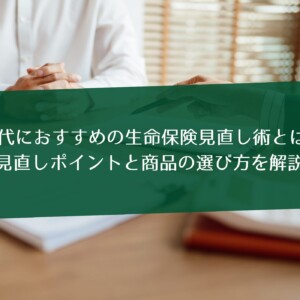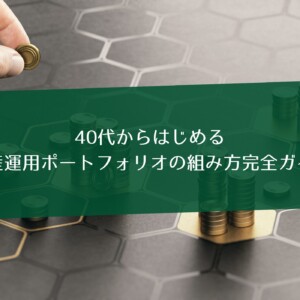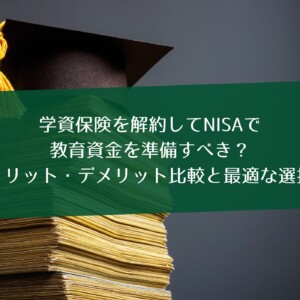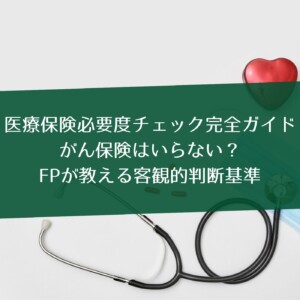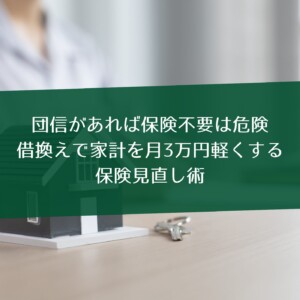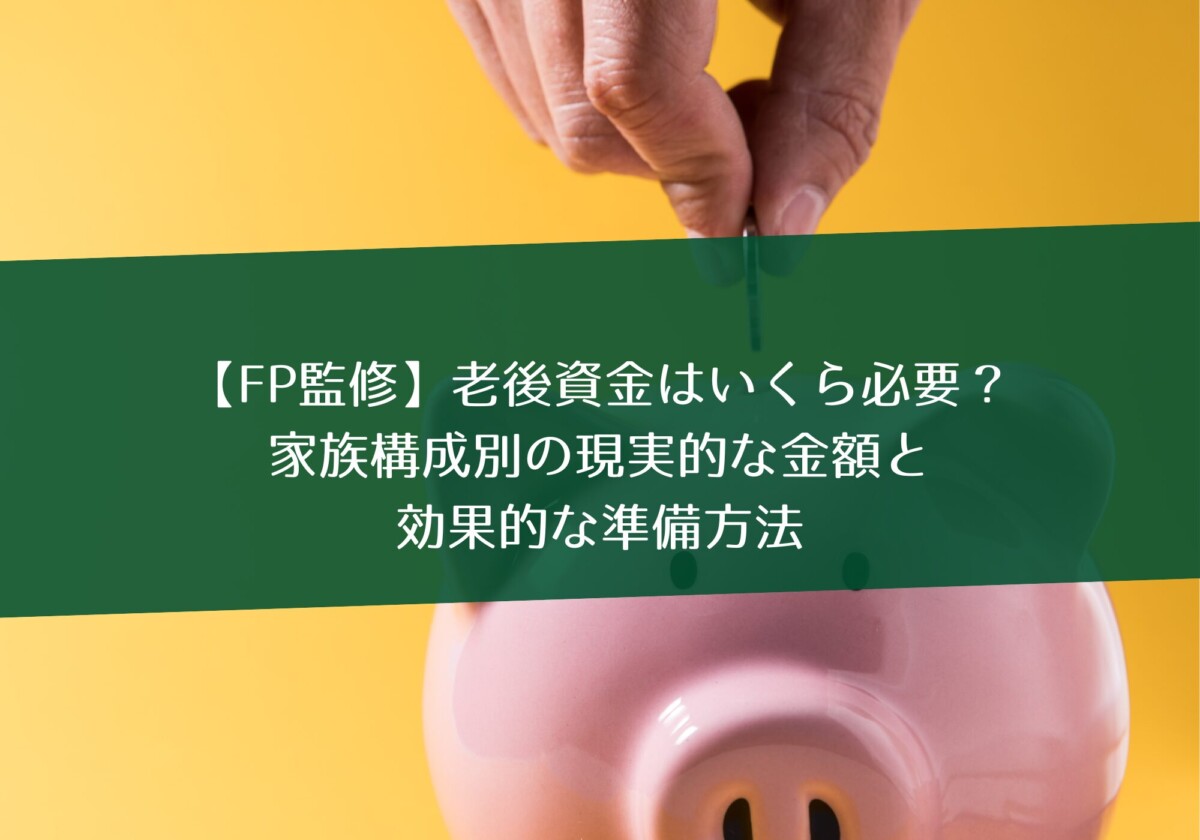
【FP監修】老後資金はいくら必要?家族構成別の現実的な金額と効果的な準備方法
あなたは老後のために十分な資金を準備できていますか?
多くの方が「老後にいくらお金が必要か」という疑問を抱えながらも、具体的な対策を取れていないのが現状です。本記事では、家族構成別に必要な老後資金の現実的な金額と、今からでも間に合う効果的な準備方法をご紹介します。なぜなら、人生100年時代と言われる今、公的年金だけでは老後の生活を十分に支えることが難しくなっているからです。ファイナンシャルプランナーの専門知識に基づき、年金とのギャップを埋める具体的な資産形成法から、年代別の準備戦略まで解説します。
この記事を読むことで、漠然とした将来への不安が、具体的な行動計画に変わるでしょう。
目次
老後に必要な資金額の真実:年金とのギャップから考える実践的な準備法
ここでは、公的年金だけでは老後の生活を十分に維持できない現実と、それを踏まえた実践的な資金準備の方法について解説します。漠然と抱いていた老後への不安を、具体的な数字に置き換えることで、より明確な目標設定と行動計画が立てられるようになります。最新の統計データに基づいた世帯別の収支ギャップを理解し、自分に必要な老後資金の目安を知ることで、今日から始められる効果的な準備法が見えてくるでしょう。
公的年金の実態と老後生活費の差額:最新統計に基づく世帯別の収支ギャップ
多くの人が頼りにしている公的年金ですが、実際の受給額と老後の生活費には大きな隔たりがあります。日本年金機構のモデル年金によると、40年間働いた平均的収入の会社員と専業主婦の世帯の年金受給額は月額約22万円。一方で、総務省の家計調査では、高齢夫婦無職世帯の平均消費支出は月額約24万円とされています。つまり、毎月約2万円の不足が生じる計算です。
このギャップはライフスタイルや世帯構成によってさらに拡大します。共働き夫婦の場合は年金受給額が増えますが、単身者や自営業者の場合は受給額が少なくなる傾向があります。特に注意すべきは、これらの統計が「平均的な生活」を前提としていることです。より充実した老後生活を望む場合、または医療費などの突発的な支出が増える場合は、さらに大きなギャップに直面する可能性があります。
今すぐできるアクション: 「ねんきん定期便」で自分の年金見込み額を確認し、現在の支出状況と比較してみましょう。具体的な数字を知ることが、効果的な準備の第一歩です。
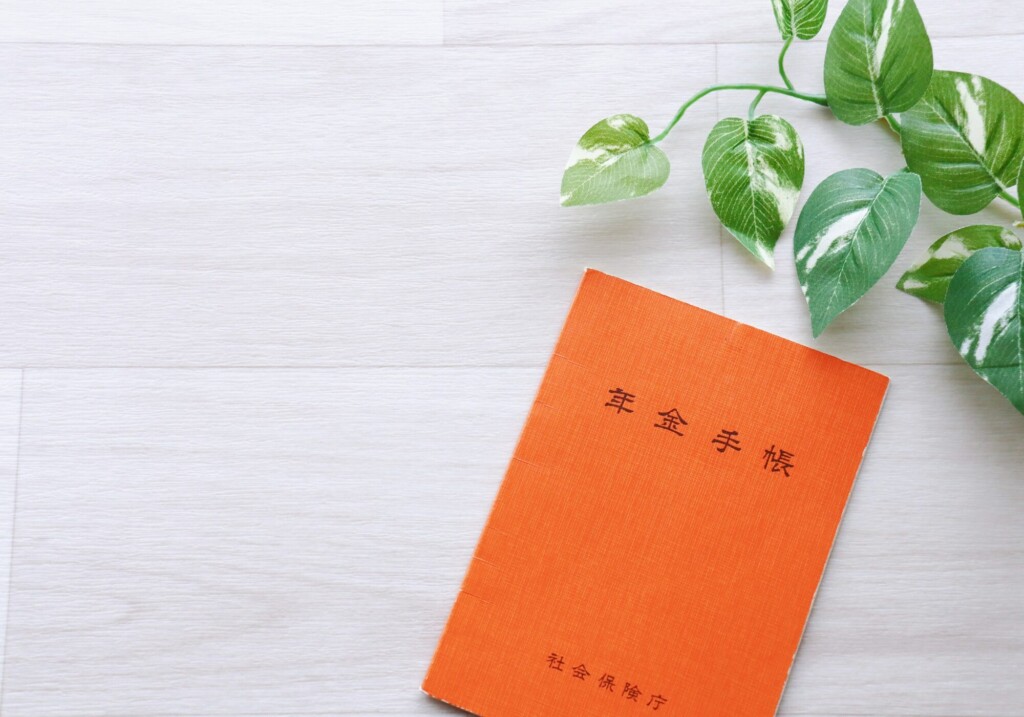
世帯構成別に必要な老後資金の目安:単身・夫婦・持ち家の有無による必要額の違い
老後に必要な資金額は世帯構成によって大きく異なります。金融庁の金融審議会報告書や総務省の家計調査を基にすると、老後30年間(65歳~95歳)に必要な資金の目安は以下のとおりです。
| 世帯構成 | 持ち家あり | 賃貸 |
|---|---|---|
| 夫婦二人 | 約2,000万円 | 約3,000万円 |
| 単身(男性) | 約1,300万円 | 約2,300万円 |
| 単身(女性) | 約1,500万円 | 約2,500万円 |
これらの金額は、公的年金を受給していることを前提に、それだけでは賄えない生活費の不足分や突発的な支出に備えるための金額です。特に持ち家の有無は必要資金額に大きく影響し、賃貸住宅に住む場合は家賃分として30年間で約1,000万円程度の追加資金が必要になります。
単身女性の場合、平均寿命が長いことから男性より多くの準備資金が推奨されています。また、生命保険文化センターの調査では、夫婦二人の場合、ゆとりある老後のためには年金に加えて毎月5~10万円の追加収入が理想的とされています。
老後の想定外支出に備える:医療費・介護費・住宅リフォーム費用の現実
老後に直面しやすい想定外の大型支出には、主に以下の3つがあります。
これらの想定外支出に備えるためには、通常の老後資金とは別に予備費として500万円程度を確保しておくことが理想的です。また、民間の医療保険や介護保険の活用も検討する価値があります。住宅関連では、住宅借入金等特別控除やバリアフリー改修促進税制などの優遇制度も利用できるため、事前に情報収集をしておきましょう。

ゆとりある老後と最低限の老後:選ぶライフスタイルで変わる必要資金の計算法
老後に必要な資金は、どのようなライフスタイルを望むかによって大きく変わります。総務省の家計調査や生命保険文化センターの調査を基に、最低限の老後生活とゆとりある老後生活の違いを比較しました。
| 費目 | 最低限の老後生活(月額) | ゆとりある老後生活(月額) |
|---|---|---|
| 食費 | 5~6万円 | 7~8万円 |
| 住居費 | 2~3万円(持ち家の場合) | 3~5万円 |
| 光熱・水道 | 2万円前後 | 2~3万円 |
| 被服費 | 5千円程度 | 1~2万円 |
| 交通・通信 | 1~2万円 | 2~3万円 |
| 教養・娯楽 | 1万円程度 | 3~5万円 |
| 交際費 | 1万円程度 | 2~3万円 |
| 合計 | 15~18万円 | 25~30万円 |
ゆとりある老後生活では、趣味や旅行、飲食を楽しむための費用が増え、最低限の生活と比べて月額10万円前後の差が生じます。この差を30年間で計算すると、約3,600万円もの開きになります。
自分が望むライフスタイルを実現するための資金を計算するには、現在の支出を項目別に洗い出し、老後に不要になるもの(子どもの教育費など)と増える可能性があるもの(医療費など)を調整します。そして公的年金の見込み額との差を埋めるために必要な金額を算出しましょう。
積極的に活用したい制度: 老後の資産形成には新NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用がおすすめです。これらの制度を利用することで、税制優遇を受けながら効率的に資産を増やすことができます。特に時間がある若いうちからの積立投資は、複利効果で大きな資産形成につながります。
老後資金を準備するための基本戦略:年代別アプローチ
ここでは、年齢層ごとに最適な老後資金準備の戦略をご紹介します。人生100年時代と言われる現在、公的年金だけに頼るのは不安という方が増えています。しかし、老後資金の準備は早く始めるほど有利ですが、どの年代からでも効果的な方法はあります。30代、40・50代、定年前後といった各ライフステージに合わせた具体的なアプローチで、あなたの将来不安を解消しましょう。今すぐ行動を起こすことで、老後の選択肢が広がり、ゆとりある生活を手に入れることができます。
30代からの老後資金準備:時間を味方につける長期積立の効果
30代からの老後資金準備には、「時間」という大きな味方があります。複利効果を最大限に活用すれば、少額からでも大きな資産形成が可能です。例えば、毎月3万円を年利3%で運用した場合、30年後には約2,030万円になります。同じ金額を投資しても、開始時期が10年遅れると最終的な資産額は半分以下になることも。
30代におすすめなのは、新NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した積立投資です。特にiDeCoは掛金が全額所得控除となる税制メリットがあり、老後資金準備の強い味方になります。投資先としては、世界経済全体の成長を取り込める「全世界株式インデックスファンド」のような、手数料の安い分散投資型の商品がおすすめです。
この年代は住宅購入や子育てなど出費も多いですが、老後資金の積立を優先的に「自動化」することがポイント。給料が入ったら真っ先に一定額を老後資金に回す習慣をつけることで、無理なく継続できます。まずは家計の固定費を見直し、月3万円からでも始めてみましょう。

40代・50代からの効率的な資産形成:限られた期間で老後資金を確保する方法
40代・50代からの老後資金準備は「効率性」がカギです。時間的制約はありますが、この年代は収入が人生でもピークを迎えることが多く、子どもの教育費が一段落する家庭も増えてきます。これらを活かして、積極的な資産形成を行いましょう。
まずは月々の積立額を増やすことが重要です。家計の無駄を徹底的に見直し、固定費を削減しましょう。通信費や保険料の見直しだけでも、年間で10万円以上浮くことも少なくありません。住宅ローンの借り換えも検討価値があります。浮いたお金を全て老後資金に回すことで、短期間でも資産形成の遅れを取り戻せます。
投資商品の選び方も重要です。リスクを取りすぎず、かといって低リターンに甘んじることもない、バランス型の資産配分が適しています。例えば、資産の60%を株式型、40%を債券型にするといった配分です。また、税制優遇のあるiDeCoや新NISAを最大限活用しましょう。特にiDeCoは年齢が上がるほど拠出できる金額が増えるため、50代の方は月額2万円(会社員の場合)まで非課税で積み立てることができます。
子どもの教育費や住宅ローンとのバランスも考慮しながら、無理のない範囲で最大限の積立を心がけましょう。

定年直前・定年後の資金管理:退職金の効果的な活用と取り崩し計画
定年前後の老後資金管理では、退職金の活用法と資金の取り崩し方が重要になります。多くの方が受け取る退職金は、使い方次第で老後の経済的安定を大きく左右します。
退職金の活用法としては、「安全資金」と「成長資金」に分けることをおすすめします。「安全資金」は生活費の2〜3年分を定期預金や普通預金などにして、いつでも使えるようにしておきます。一方「成長資金」は中長期での資産増加を目指し、分散投資で運用します。このバランスは個人のリスク許容度によって調整する必要がありますが、長寿リスクを考えるとある程度の成長性を確保することも大切です。
資金の取り崩し方も計画的に行いましょう。退職金の使い方としては、目的別に「短期資金」「中期資金」「長期資金」に分けて考えるとよいでしょう。短期資金は当面の生活費に、中期資金は5年以内に使うお金に、長期資金は75歳以降に使うお金に充てるのが一般的です。例えば2,000万円の資産があれば、年間80万円(月約6.7万円)の取り崩しなら長期間持続できる可能性が高いとされています。
また、公的年金の受給開始時期も検討しましょう。繰り下げ受給を選べば、最大で42%増額された年金を生涯受け取れます。健康状態や家族歴を考慮しながら、最適な選択をしてください。
老後準備の開始時期による必要積立額の違い:早期開始のメリットを数値で確認
老後資金準備の開始時期によって、目標金額を達成するために必要な月々の積立額は大きく変わってきます。下の表は、65歳までに2,000万円の老後資金を用意する場合の、開始年齢別の必要積立額(年利3%で運用と仮定)です。
| 開始年齢 | 積立期間 | 必要な月々の積立額 | 総積立額 | 運用益 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳 | 35年 | 約2.8万円 | 約1,176万円 | 約824万円 |
| 40歳 | 25年 | 約4.5万円 | 約1,350万円 | 約650万円 |
| 50歳 | 15年 | 約8.7万円 | 約1,566万円 | 約434万円 |
| 55歳 | 10年 | 約14.1万円 | 約1,692万円 | 約308万円 |
この表からわかるように、開始時期が10年遅れるごとに、必要な月々の積立額は約1.6倍に増加します。特に50代からの場合、30代から始める場合の約3倍の金額が必要になるのです。これは複利効果によるもので、早く始めるほど「時間」がお金を増やしてくれるという原理です。
また、積立総額と目標金額の差である「運用益」の部分に注目すると、30歳から始めた場合は約824万円と、目標額の40%以上を運用益が占めています。一方、55歳からでは約308万円と、目標額の15%程度にとどまります。
これらの数字は、老後資金準備は一日でも早く始めることの重要性を示しています。今日から行動を起こして、将来のゆとりある老後生活に向けた第一歩を踏み出しましょう。
老後資金を効率的に増やす資産形成手法:制度と商品の選び方
ここでは、老後資金を効率よく増やすための様々な金融商品や制度をご紹介します。単なる貯金では物価上昇に負けてしまう時代、資産を「育てる」視点が不可欠です。新NISA・iDeCo・投資信託・保険商品など、それぞれの特徴やメリットを理解し、自分のライフプランに合った選択をすることで、老後の資金不足への不安を解消できます。今すぐ行動を起こして、将来のゆとりある生活のための準備を始めましょう。金融商品をうまく活用することで、同じ金額でもより効率的に資産形成が可能になります。
新NISA制度の活用法:非課税枠を最大限に活かした長期投資戦略
新NISA制度は、投資で得た利益に対して税金がかからない優れた制度です。2024年からはつみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の2種類になり、合計360万円まで非課税で投資できるようになりました。この枠を最大限活用することで、老後資金形成を大きく加速させることが可能です。
特につみたて投資枠は、少額から定期的に投資できる「積立投資」に適しており、投資初心者の方にもおすすめです。例えば、毎月3万円を30年間つみたて投資すると、年利3%の場合、総投資額1,080万円が約1,700万円に成長する可能性があります。成長投資枠は、一括投資や幅広い金融商品への投資が可能で、ある程度投資経験のある方に向いています。
新NISAを活用する際のポイントは、長期投資を前提に商品を選ぶことです。短期的な値動きに一喜一憂せず、世界経済全体の成長を取り込める「全世界株式インデックスファンド」などの低コスト商品を中心に考えるとよいでしょう。また、毎月の積立日を給料日直後に設定することで、無理なく継続できる仕組みを作ることも大切です。
>> NISAは今やるべきか?2024年からの新制度で迷う人へ完全ガイド
iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用ポイント:税制メリットと運用商品の選択基準
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金形成において非常に優れた制度です。その最大の魅力は「3つの税制メリット」にあります。①掛金が全額所得控除になり、所得税・住民税が軽減される「拠出時の優遇」、②運用益が非課税になる「運用中の優遇」、③受取時に退職所得控除や公的年金等控除が適用される「受取時の優遇」があり、これらを総合すると通常の投資に比べて大きなアドバンテージとなります。
掛金の上限額は職業によって異なり、会社員(企業年金なし)であれば月額2.3万円、自営業者なら月額6.8万円まで拠出可能です。なお、2025年の税制改正では掛金上限額の引き上げが予定されています。運用商品の選択は、長期的な視点で行うことが重要で、若いうちは株式比率を高め、退職年齢に近づくにつれて安全資産の比率を高めていく「ライフサイクル戦略」が一般的です。
次の表は、新NISAとiDeCoの主な特徴を比較したものです。
| 項目 | 新NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間360万円(つみたて枠120万円+成長枠240万円) | 月額1.2万円~6.8万円(職業により異なる) |
| 税制優遇 | 運用益が非課税 | 掛金全額が所得控除+運用益非課税+受取時の税制優遇 |
| 資金の引出 | いつでも可能 | 原則60歳まで引き出し不可 |
| 商品選択 | 幅広い金融商品 | 加入する金融機関が提供する商品のみ |
| 向いている人 | 資金の柔軟性を重視する人 | 税制優遇を最大限に活用したい人 |
この表からわかるように、どちらも優れた制度ですが、特性が異なります。理想的には、iDeCoで税制メリットを最大化しつつ、新NISAで資金の柔軟性も確保するという組み合わせがおすすめです。まずはライフプランに合わせて、無理のない範囲でiDeCoから始めてみましょう。
投資信託を活用した資産形成:分散投資で安定的に資産を育てる実践手法
投資信託は、多くの投資家から集めたお金をプロの運用者が様々な金融商品に分散投資する商品です。一人では難しい分散投資が少額から始められるため、老後資金形成において非常に有効なツールとなります。特に長期・積立・分散という3原則を守ることで、市場の短期的な変動に左右されず、安定的に資産を育てることが可能です。
投資信託を選ぶ際の重要なポイントは以下の3つです。
初心者におすすめなのは、世界中の株式に幅広く投資する「全世界株式インデックスファンド」です。これ一つで世界経済全体の成長を取り込むことができます。リスクを抑えたい場合は、株式と債券をバランスよく組み合わせた「バランスファンド」も選択肢となります。
年代別の資産配分の目安としては、「100-年齢」を株式の配分率(%)とする方法があります。例えば40歳なら株式60%・債券40%といった具合です。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個人のリスク許容度や市場環境によって調整が必要です。ただし、これはあくまで目安であり、自分のリスク許容度に合わせて調整することが大切です。
投資信託での資産形成を始める際は、まず月3,000円から「つみたてNISA」などの非課税制度を利用して積立投資を習慣化することから始めましょう。市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で継続することが成功の鍵です。

保険商品の老後資金対策:個人年金保険と終身保険の活用シーン
保険商品も老後資金形成の選択肢の一つです。特に個人年金保険と終身保険は、安定性を重視する方や、投資に不安を感じる方にとって有効な手段となります。
個人年金保険は、契約期間中に保険料を払い込み、年金受取開始年齢以降に年金として受け取る商品です。受取方法は「確定年金型」(一定期間受け取る方式)と「終身年金型」(生涯にわたって受け取る方式)があり、長生きリスクに備えるなら後者がおすすめです。最近は「変額個人年金保険」という、運用成果によって将来の年金額が変動するタイプも人気ですが、元本割れリスクもあるため、自分のリスク許容度を考慮して選ぶことが重要です。
終身保険も老後資金対策として活用できます。保険金は亡くなった際に遺族に支払われますが、「解約返戻金」として中途解約時に資金を受け取ることも可能です。特に「低解約返戻金型終身保険」は保険料が割安で、貯蓄性よりも保障を重視する方に向いています。一方、「高解約返戻金型終身保険」は保険料は高めですが、貯蓄性が高く、60代以降の解約を前提とした老後資金対策として検討する価値があります。ただし、保険商品はインフレリスクに弱い面があるため、その点も考慮する必要があります。
保険商品を選ぶ際は、手数料や解約返戻金の推移を必ず確認しましょう。特に若いうちは保険よりも投資信託などの成長性の高い商品が有利ですが、高齢になるにつれて安定性の高い保険商品の割合を増やしていくという組み合わせ方が理想的です。商品選びに迷ったら、ファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの方法です。
いずれの保険商品も、契約前に複数の会社の商品を比較し、自分のライフプランに最も適したものを選ぶことが大切です。また、加入後も定期的に見直しを行い、状況の変化に応じて調整していくことをおすすめします。
老後資金計画の実践と見直し:確実に目標を達成するための管理法
ここでは、老後資金計画を立てるだけでなく、確実に実行し続けるための具体的な方法をご紹介します。計画を立てても実行できなければ意味がありません。日々の家計管理から定期的な見直し、そしてプロの助言の活用まで、実践的なアプローチを知ることで、変化の激しい時代でも揺るがない老後資金計画を維持できるようになります。特に重要なのは、計画を「立てっぱなし」にせず、ライフイベントや経済状況の変化に合わせて柔軟に調整していくことです。この章で紹介する方法を実践すれば、老後の不安を確実な安心に変えることができるでしょう。
家計の見直しで捻出する老後資金:固定費削減と収入アップの現実的な方法
老後資金の準備は、大きな額を一度に用意するのではなく、日々の家計から少しずつ捻出することが現実的です。まず注目すべきは「固定費」の見直しです。特に大きな固定費である「住宅」「保険」「通信費」の3つを見直すだけでも、月に数万円の節約が可能になることがあります。
住宅ローンは金利の低い今こそ借り換えのチャンスです。わずか0.5%の金利差でも、3,000万円の残債がある場合、総返済額で約80万円もの差が生じます。保険については、掛け捨てから貯蓄性、医療から生命まで様々な種類がありますが、本当に必要な保障は何かを考え直してみましょう。家族構成や年齢に合わせた見直しで、月1万円以上の節約も可能です。通信費も競争が激化している今、乗り換えるだけで大きな節約になることがあります。
今日からできるアクション: 3大固定費の見直しから始めましょう。住宅ローンの借り換えシミュレーション、保険の証券確認、通信費の他社比較を今週中に行い、「行動計画表」に記録してください。小さな節約でも、これを毎月の老後資金積立に回せば、30年後には大きな差となって表れます。

インフレリスクへの対策:老後資金の実質的な価値を維持するための運用戦略
インフレは老後資金にとって「目に見えない敵」です。年率2%のインフレが30年続くと、1,000万円の価値は約552万円にまで目減りしてしまいます。このリスクに対抗するには、単なる貯金ではなく、インフレに負けない「資産運用」が不可欠です。
運用戦略の基本は「分散投資」です。株式・債券・不動産など性質の異なる資産に分散して投資することで、リスクを抑えながらインフレに勝る収益を目指します。特に株式は長期的に見るとインフレを上回るリターンをもたらす傾向があり、インフレヘッジとして有効です。
年齢や個人の状況によって適切な資産配分は大きく異なります。一般的な目安として、以下のような配分が提案されることがありますが、これはあくまで参考程度にとどめ、個人の状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。
| 年齢層 | 成長性資産(株式等) | 安定性資産(債券・預金等) |
|---|---|---|
| 30〜40代 | 60〜80% | 20〜40% |
| 50代 | 40〜60% | 40〜60% |
| 60代以降 | 20〜40% | 60〜80% |
ただし、この割合はあくまで目安であり、個人のリスク許容度や目標に合わせて調整する必要があります。老後資金の運用では、高いリターンを追求するよりも、インフレに負けない程度の収益を安定的に確保することが重要です。
新NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用すれば、さらに効率的な資産形成が可能になります。iDeCoは掛金全額が所得控除され、運用益も非課税となるため、税制優遇を活用した資産形成に有効です。ただし、60歳まで原則として引き出せないことや、運用次第では元本割れのリスクもあることに注意が必要です。

ライフプランの変化に応じた老後資金計画の調整:定期的な見直しのタイミングと方法
人生は予測不可能な変化の連続です。老後資金計画も固定的なものではなく、ライフイベントや経済環境の変化に応じて柔軟に見直していく必要があります。特に以下のタイミングでは、必ず計画を見直しましょう。
見直しの基本的な流れは、まず現在の資産状況と収支を再確認し、目標額や達成期間を調整することから始めます。例えば、昇進して収入が増えた場合は積立額を増やす、子どもの教育費が一段落した場合は老後資金へのシフトを強化するといった対応が考えられます。
特に重要なのは、年に一度は「資産棚卸し」を行うことです。貯蓄、投資、保険、年金など全ての資産を洗い出し、目標に対する進捗状況を確認します。その際、金融機関からの通知やねんきん定期便などを活用すると、より正確な状況把握が可能です。
見直しのポイント: 環境の変化に応じて計画を柔軟に変更することは必要ですが、資産運用の基本方針(例:長期・分散・積立)は一貫して守ることが大切です。市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持ち続けましょう。
専門家の相談活用法:FPに相談するとよい状況と相談時の準備ポイント
自分だけで老後資金計画を立てるのは難しいと感じる場合、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が有効です。特に以下のような状況では、プロの知識やアドバイスが大きな助けとなります。
FPへの相談を効果的に行うには、事前の準備が重要です。以下の情報を整理しておくと、より具体的で役立つアドバイスを得られるでしょう。
FP選びのポイントは、報酬体系を確認することです。相談料のみのフィーオンリー型、金融商品の販売手数料で収入を得るタイプ、その両方を組み合わせたタイプなど様々です。また、得意分野や相性も重要な選択基準となります。一度の相談で即決せず、複数のFPに相談することで、より客観的な判断ができるようになります。
相談の頻度: 初回の相談後も、年に1回程度の定期的な相談がおすすめです。特に大きなライフイベントの前後や、経済環境・税制に大きな変化があった際には、積極的に相談することで、より効果的な老後資金計画の調整が可能になります。

まとめ
この記事をお読みいただき、ありがとうございます。老後に備えた資金計画は、誰もが考えなければならない重要なテーマです。人生100年時代といわれる今、自分らしい老後生活を実現するためには、早めの準備と正しい知識が不可欠です。ここで紹介した内容が、皆様の将来への不安を少しでも解消し、具体的な行動のきっかけとなれば幸いです。改めて、この記事の重要なポイントをまとめたいと思います。
- 公的年金だけでは老後生活費をカバーできないケースが多く、世帯構成に応じた追加資金の準備が必要である
- 早期に老後資金準備を始めるほど効果的で、30代から始めれば少額の積立でも複利効果により大きな資産形成が可能となる
- 新NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用することで、同じ金額でもより効率的に資産を増やすことができる
- インフレリスクに備えるには、単なる貯蓄だけでなく適切な資産運用が重要である
- ライフイベントに合わせた定期的な計画の見直しが老後資金計画成功の鍵となる
老後資金の準備は早く始めるほど有利ですが、どの年代からでも効果的な準備は可能です。大切なのは「今日から行動を起こすこと」です。自分の現状を正確に把握し、ライフスタイルに合った目標を設定して、着実に準備を進めましょう。不安や疑問がある場合は、ファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの方法です。みらい資産研究所では、お客様一人ひとりに合わせた老後資金計画のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。